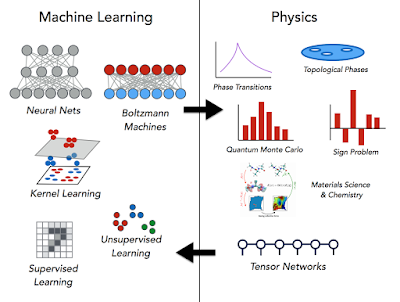誕生日
今日で70歳になります。seventyです。よく似ていますが、seventeenではありません。 いつも誕生日のたびに、ふざけた文章を投稿していたのですが、今年からやめることにしました。ちょっと周回遅れかもしれませんが、今年の目標は、「大人」になることです。 近況です。 これまで遊んでいながらでもできたことが、できなくなっているのを感じます。トップ・ランカーだった「キャンディー・クラッシュ」やめました。かわりに「数独」はじめました。 AlexaでSpotifyが呼べないので困っています。Google Play MusicやNMLナクソスは、最初から諦めていたのですが、Spotfyがダメだとは思っていませんでした。手動で「グローバル・ヒット Top 50 」聞いています 年相応に、健康に留意しなければいけないと思って、電子タバコに変えてみたのですが、電子タバコも無害ではないと言う記事を読み、電子タバコやめました。 マルレク+MaruLaboの「量子機械学習」系の活動の他に、次のようなことができればと思っています。 ・「知識表現と意味理解」研究会みたいなのを作りたいと思っています。本当は、一緒に「認知と推論メカニズム」といった研究会もあればいいと思っているのですが。 ・「数学」あるいは「数学の哲学」について語る場を作りたいのです。当面、単発の企画から始めようかと思っています。 ・可能であれば、才能のある若い人たちをエンカレッジする活動ができればと思っています。(「エンカレッジする」と言っている僕には、相変わらず、「お金」にも「権威」にも縁がないのですが。) 「大人」になった丸山、今年も、生暖かく見守ってください。